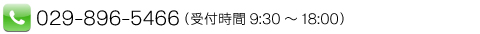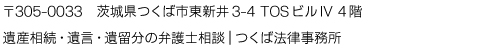相続の効力に関する見直し
「相続させる」旨の遺言がある場合の相続の効力の見直し
《相続の効力と登記》
被相続人の死亡により、相続が開始した場合、相続財産は共同相続人の共有となります。各共同相続人は、相続財産のうちの不動産について、相続に基づく登記を備えなくとも(不動産の登記名義が被相続人のままであっても)、自己の法定相続分の範囲で持分を第三者に主張することができます(最判昭和38・2・22)。
これを第三者の側から見ると、例えば一部の共同相続人の債権者は、被相続人の登記名義のままである相続財産を構成する不動産について、当該共同相続人が法定相続分の範囲で被相続人所有の不動産について持分を有すると主張して、その持分について差押えをすることができます。
法定相続分と異なる遺産分割により、共同相続人のうちの一人が相続財産を構成するある不動産を単独で取得した場合、法定相続分の範囲における持分については相続登記なくして第三者に主張することができます。
対して、法定相続分を超える部分の権利の取得の効力と上記のような法定相続分による差押えとの優劣は、遺産分割に基づく相続登記と差押の先後により決まります。つまり、法定相続分と異なる遺産分割が成立しても、その旨の相続登記がされない間に法定相続分に基づく差押えがされて登記が供えられた場合、相続人はその差押えの効力を否定することはできません(最判昭和46・1・26)。
遺贈の場合でも同様の結論となります。
《改正前の制度の問題点》
改正前の制度では、特定の相続財産を一部の相続人に相続させる旨の遺言があった場合、被相続人の債権者(相続債権者)等の第三者を害する結果を生じさせることがありました。
(具体例)
被相続人Aが死亡し、相続人が子B及び子Cであった場合において、相続債権者が自己の相続債権の回収のため、Aの遺産に属する登記名義が被相続人であるAのままである不動産について、Cの法定相続分で差押えをしようとしました。
ところが、Aが遺言によりその不動産をBに相続させることとしていた場合、判例上(最判平成14・6・10)、Bはその不動産の取得を第三者に登記なくして主張することができるとされており、相続債権者はCの法定相続分による差押えをすることができなくなってしまいます。
判例によれば、「相続させる」旨の遺言による相続は、法定相続分に基づく相続と本質的に異ならないと考えられているのです。
このような結論は、遺言の存在を知りえない第三者に予想しえない不利益を被らせることとなっていました。
《改正後の制度》
上記のような問題に対処するため、法改正により、法定相続分を超える相続については、遺産の取得方法が、遺言によるものか、遺産分割によるものかの方法の如何を問わず、相続の登記をしなければその相続の効力を第三者に主張することができないこととされました(民法899条の2)。この改正法の施行日は令和元年7月1日であり、施行日以後に開始した相続について適用されます。
上記の(具体例)の場合において、相続債権者によるCの持分についての差押えと、Bの遺言による不動産の相続の優劣は、登記の先後により決まることとなり、先に述べた遺産分割や遺贈による特定の不動産の相続の場合と同様の帰結をとることとされました。
これにより、被相続人の登記名義のままとなっているという登記を信頼した第三者に予想外の不利益を被らせることを防ぐことができるようになりました。
遺言による相続分の指定がある場合の相続債権者の権利行使
平成30年の法改正により、遺言により相続分の指定がある場合の相続債権者の債権の行使方法についての判例法理(最判平成21・3・24)が明文化されました(民法902条の2)。
民法902条の2によれば、遺言による相続分の指定を知りえない相続債権者は、法定相続分に基づいて各共同相続人に対し、債権を行使することができることとされています。ただし、指 定相続分の通りの相続の承認、すなわち指定相続分に基づく債務の承継を承認した相続債権者は指定相続分に基づいて債権を行使することができます。
この規定は、遺言による相続分の指定を通常知りえない相続債権者保護する趣旨のものであるといえます。